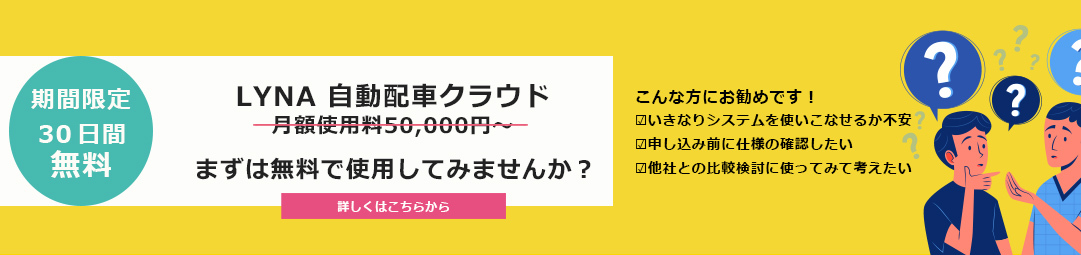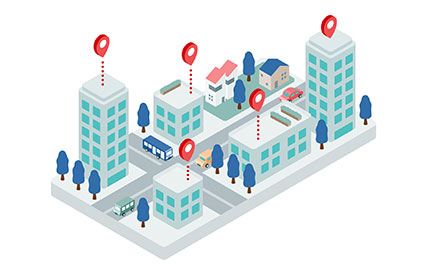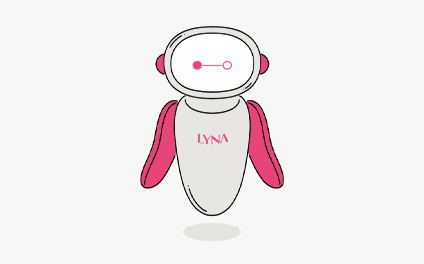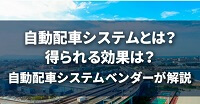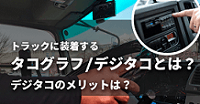初心者向けかんたん物流コラム
2023年8月最新【アルコールチェック義務化】対象者や方法は?いつから始まる?

公開日:2022年11月2日
最終更新日:2023年8月15日
白ナンバー車を一定台数以上使用する事業者に対してのアルコールチェック義務化の施行がはじまっています。
2022年4月から、運転前後にドライバーの酒気帯びの有無を目視で確認することなどが義務となりました。
さらに2023年12月からは、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認も義務化されます。
対象者や方法などアルコールチェック義務化に関わる情報をまとめました。ご参考いただければ幸いです。
※当記事は2023年8月10日時点の情報を基にしています。
【白ナンバーと緑ナンバーの違いを詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめ!】
白ナンバートラックとは?できること・違法なこと・緑ナンバートラックとの違い
自動配車ベンダーが作成したエクセル配車表を無料でダウンロードいただけます。
事前にちょこっと情報を登録しておけば、かんたんなマウス操作だけで配車スケジュールを作成できたり、配送先までのおおよその移動距離・時間が自動で計算されたりという、とても便利なエクセル配車表です。
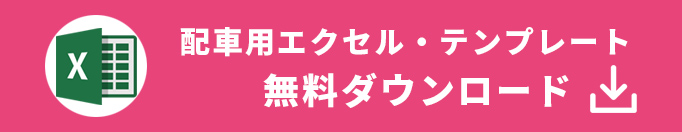
目次
アルコールチェックが義務化!一定台数以上の白ナンバー車を持つ事業所にも
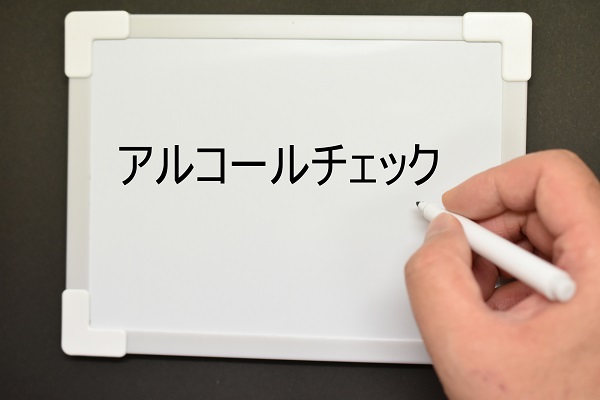
2021年11月、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これにより、一定台数以上の白ナンバーの車を持つ事業所にもアルコールチェックが義務付けられることになりました。
これまでは、選任された安全運転管理者がドライバーに対し、正常な運転をすることができないおそれがないかを確認する必要はありましたが、具体的方法に基づいたアルコールチェックは義務付けられておらず、事業者の意識や取り組みにかかっているところがありました。
アルコールチェックの義務化は先に2011年に緑ナンバーの事業者に適用されていましたが、道路交通法施行規則の改正でその適用範囲が広がったことになります。
アルコールチェック義務化の対象となるのは?

アルコールチェック義務化は、「白ナンバー車を5台以上」または「11人以上の定員の白ナンバー車を1台以上」保有している事業所が対象になります。
言い換えれば、上記は安全運転管理者を選任しなければならない事業所となりますので、「安全運転管理者を選任している事業所がアルコールチェック義務化の対象になる」ということです。
警察庁によりますと、安全運転管理者を選任している事業所は2023年3月末時点で全国で約39万(管理下のドライバーは約869万人)にも及ぶとしており、非常に多くの事業所が対象になります。
【アルコールチェック義務化が対象となる事業所】
・白ナンバー車を5台以上保有している事業所
・11人以上の定員の白ナンバー車を1台以上保有している事業所
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算
アルコールチェックの方法は?義務化はいつから?
アルコールチェック義務化はすでに施行されています。
当該事業所には2022年4月から、運転前後にドライバーの酒気帯びの有無を目視で確認することや、検査記録を1年間保存することなどが義務付けられるようになりました。さらに2023年12月1日からは、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認も義務化されます。
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認に関しては、下の網掛け部分にあるように2022年10月1日からの施行が予定されていましたが、半導体不足などによるアルコール検知器の供給不足があったことから延期されていました。
しかしながら2023年8月8日、警察庁から2023年12月1日からの施行で決定したと発表がありました。検知器メーカーの団体や対象事業者などへの調査から、アルコール検知器が十分に供給できる状態にあると判断したとのことです。
●令和4年4月1日施行分
・運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・上記の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること
●令和4年10月1日施行分 → 令和5年12月1日から施行
・ アルコール検知器を用いて上記の確認を行うこと
・ アルコール検知器を常時有効に保持すること
※出典:警察庁「「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について」
自動配車ベンダーが作成したエクセル配車表を無料でダウンロードいただけます。
事前にちょこっと情報を登録しておけば、かんたんなマウス操作だけで配車スケジュールを作成できたり、配送先までのおおよその移動距離・時間が自動で計算されたりという、とても便利なエクセル配車表です。
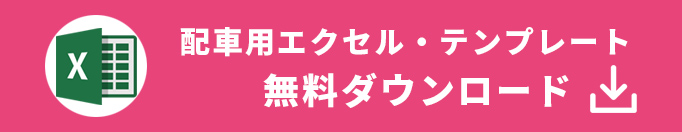
アルコールチェック「運転者の状態を目視等で確認すること」とは?
2022年4月から施行されているアルコールチェックの方法に、「運転者の状態を目視等で確認すること」とあります。ただ、具体的にはどのように行えば良いのか、疑問に思った方も多いのではないでしょうか?岩手県警察の公式サイトに以下のように書かれていました。
運転者の「顔色」、「呼気の臭い」、「応答の声の調子」などで確認することです。
※出典:岩手県警察公式サイト「安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化」
また、これについては、愛知県警察公式チャンネルの動画内でも解説されています。こちらに引用させていただきます。
合わせてご覧ください。
直行直帰をする場合のアルコールチェックはどうすれば?
目視確認によるアルコールチェックについてもう一つ。原則、対面で行うこととされています。しかしながら業務上、どうしても対面で目視確認をすることができない状況もあるかと思います。ドライバーが直行直帰をする場合です。
例えば、営業職の方の場合、客先が遠方となれば営業車を使って直行直帰をすることもあるかと思います。このような場合はどのようにアルコールチェックを行えば良いのでしょうか。警察庁は以下のような考え方を示しています。
対面での目視が原則だが、困難な場合はこれに準ずる適宜の方法で実施すればよい。
(適宜の方法の例)
運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
・カメラ、モニター等によって、運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、検知器による測定結果を確認する方法
・電話等によって、運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、検知器による測定結果を報告させる方法
※出典:警察庁「「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について」
アルコールチェック義務化の背景
白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務化されることになった背景には、2021年6月に千葉県八街市で起こった白ナンバートラックによる飲酒運転事故があります。児童5人を死傷させるという大変痛ましい事故でした。
事故を起こしたドライバーは昼食時に高速道路のサービスエリアで飲酒をしたとされ、事業者側も普段からアルコールチェックは行っていなかったようです。事業者は白ナンバートラックを2台所有していましたが、具体的方法に基づいたアルコールチェックが義務となる対象者ではなかったのです。
この事故が大きなきっかけとなり、白ナンバー事業者にも緑ナンバー事業者同様のアルコールチェックが義務化されるよう、道路交通法施行規則の一部改正が行われることになりました。
アルコールチェックを怠った場合の罰則
安全運転管理者がアルコールチェックを怠ったとしても直接的な罰則はありません。しかしながら、安全運転管理者がアルコールチェックを怠ることにより、安全な運転の確保がされていないと認められる場合には、都道府県公安委員会による安全運転管理者の解任命令の対象になります。
また、アルコールチェックを怠ることに対しての罰則はありませんが、飲酒運転をすること自体が悪質な犯罪です。従業員であるドライバーが飲酒運転を犯した場合、罰則が科されるのはドライバーだけではありません。道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」違反にあたり、代表者や管理責任者にも「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い罰則が科される恐れがあります。
まとめ:飲酒運転は悪質な犯罪
白ナンバー事業者へのアルコールチェック義務化の施行はすでにはじまっており、安全運転管理者を選任している事業所は、その対象となります。
2023年12月1日からは、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認も義務化されます。
飲酒運転は悪質な犯罪です。企業としても改めて大きな問題と捉えて、アルコールチェックをはじめとした飲酒運転防止のための取り組みを徹底していくことが必要となります。
自社の荷物を運ぶために車を使用している白ナンバー事業者は今後2024年問題への対応も
今後、自社の荷物を運ぶために車を使用している白ナンバー事業者は、アルコール検知器によるアルコールチェック義務化への対応とともに、いわゆる2024年問題への対応も必要となってきます。2024年4月からドライバー(自動車運転業務)に対し、年960時間の時間外労働の上限規制がかかってくることから、ドライバーの残業が多くなっている場合は労働時間管理や業務管理の徹底がこれまで以上に必要になります。
その際、労働時間管理や業務管理を正確にかつ容易に行えるようにするためには、デジタルツールの活用が効果的です。弊社では、効率の良い配送計画を自動で作成したり配送業務の可視化・管理が容易に行えたりする自動配車システムを提供しております。デジタルツール導入のご検討の際は、ぜひ一度お試しください。
弊社の主力製品である「LYNA 自動配車クラウド」は30日間の無料試用を承っております(無料試用期間中は全ての標準機能を試用可能)。
どうぞお気軽にお問い合わせください。